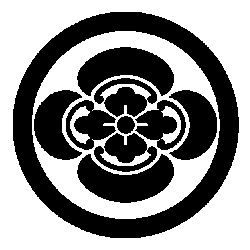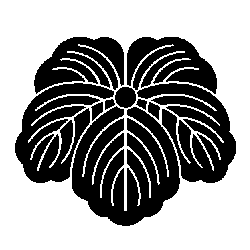探索レポート その三
探索レポート その三
初出 1998. 8. 8 最終更新 2001. 6.24
家紋について
| 名前 | 出身地 | 家紋 | 宗派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高坂(父方) | 岡山市足守町大井 | 「丸に横木瓜」 | 天台宗 | - |
| 石田(母方) | 岡山県総社市 | 「丸に隅立て四つ目」 | 日蓮宗 | 池田藩の槍持ちだった? |
| 遠藤(妻の父方) | 北海道岩見沢市 | ? | 浄土真宗大谷派東本願寺 | - |
| 崎山(妻の母方) | 北海道室蘭市祝津 | 「蔦」 | 浄土真宗大谷派東本願寺 | 元々は福井出身? |
|
去年の12月に、高坂佳和さんから、「家紋を調べると面白いかも知れませんね」というメイルをいただきましたが、無精している間にもう8月になってしまいました。 やっとその気になって調べてみたら、結構面白いですね。家紋は、単にグラフィックデザインとしてみても、美しく洗練されています。日本古来の色、柄、デザインはもっともっと見直されても良いと思いました。古い物をそのまま現代に生かすことは難しいですが、紋章を作る発想ややり方を現代に生かすことは、温故知新の言葉通りではないかと思います。 下記の書物とホームページを参考に、ここ数日で分かった事をまとめてみます。 因みに、高坂佳和さんの家紋は「目結紋」(めゆいもん)の中の「隅立て四つ目」(すみだてよつめ)でした。
・「日本姓氏紋章総覧」新人物往来社 \1262
<由来>
平安時代に、お公家さんが牛車の車輪を模様化して使い初め、特に、近衛家では華麗な「近衛牡丹」といわれる物を紋章として使用したことから、始まったと言われています。 <種類> 約2万種類あり、様々なバリエーションを菊系統とか菱系統などの基本的な物にまとめると約400種類だそうです。2万種を分類すると、植物が四分の一、続いて用具、中国伝来の文様、動物、自然、文字などあらゆる物を紋章化しています。 今で言う、キャラクターデザイン、ブランドネームの役割ですが、一時期、一世を風靡したCI(コーポレートアイデンティティ)の日本版と言っても良いでしょう。 西欧の紋章と、その成り立ちや役割がほとんど同じであるのは面白いですね。
両親や妻の親戚に聞いてみた結果を上の表にまとめてみました。我が家では、「丸に横木瓜」が定紋、「蔦」が女紋となるわけです。
「木瓜紋」は日本で二番目に多い紋だそうです。もともとは但馬の日下部氏から始まり、越前の浅倉氏、織田氏も「木瓜紋」だそうです。
特に北陸一円に多く、戦国時代には借り出された農民達も、「木瓜紋」を借用し、名門浅倉家中を誇ったために、広がったといわれています。
ありふれているのは一寸つまらないですが、それだけ勢力を持っていた集団が広めたのか、愛された紋なのでしょうね。 「蔦紋」は樹木に絡まって繁殖する、その旺盛な生命力とシンプルな形で、江戸時代の庶民に人気があり、八代将軍吉宗も「葵紋」とは別に「蔦紋」を替紋として使っていたそうです。 25番目に多い家紋。 <高坂姓の家紋>
我が家の家紋は「丸に横木瓜」、高坂佳和さんの家紋は「隅立て四つ目」でした。
じゃあ、いつも出てくる高坂昌信の家紋は何かと思ったのですが、いざ調べようと思うとなかなか情報が無いですね。武田信玄の「武田菱」は頻繁に出てくるのですが、高坂昌信の家紋に言及している物は今のところ無いようです。今後、気を付けて探してみたいと思っています。 |